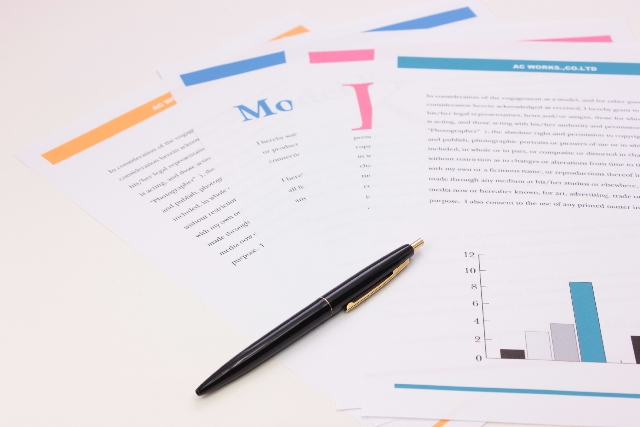


雇用保険 健康保険 年金に詳しい方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。
9月に退職した際の事で聞きたいのですが、
退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?
退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。
失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。
9月に退職した際の事で聞きたいのですが、
退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?
退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。
失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
貴方は契約の更新を望むが派遣元が契約を更新しないのであれば会社都合と言う事で雇用保険では「特定受給資格者」として認定されるでしょう(離職票に派遣元が会社都合と書いた場合です)
健康保険・年金は、もちろんですがすべて貴方の負担です。
社会保険は2年間は任意継続が出来ますが、会社が負担していた分も貴方の負担になるので現在の倍近い保険料になります。
扶養に入るのは難しいでしょう、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入れません。
国民健康保険へ切り替えられた方がたぶん安くなるなるでしょう、雇用保険受給資格者証を役所の国民健康保険の手続きの際に持参してください、失業中と言う事で保険料が減額されることがあります。
年金は最寄りの日本年金機構(旧社会保険事務所)で国民年金への切替えとなりますが、これも失業中は免除や減額の制度があります。
健康保険・年金は、もちろんですがすべて貴方の負担です。
社会保険は2年間は任意継続が出来ますが、会社が負担していた分も貴方の負担になるので現在の倍近い保険料になります。
扶養に入るのは難しいでしょう、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入れません。
国民健康保険へ切り替えられた方がたぶん安くなるなるでしょう、雇用保険受給資格者証を役所の国民健康保険の手続きの際に持参してください、失業中と言う事で保険料が減額されることがあります。
年金は最寄りの日本年金機構(旧社会保険事務所)で国民年金への切替えとなりますが、これも失業中は免除や減額の制度があります。
■国民保険について
私は11月末で会社を自己都合で退職しました。失業保険?の申請をし、すぐに仕事も見つかると思い、国民保険に切り替えなかったんですが、
急に保険証が必要になり、お金を納めようと思っています。
■だいたい一月にどれくらい納めるものなのでしょうか?以前は年180万程度の収入でした。又、減らしてもらえるでしょうか?
■すぐに保険証、又は代わりの物などは発行してもらえるのでしょうか?
私は11月末で会社を自己都合で退職しました。失業保険?の申請をし、すぐに仕事も見つかると思い、国民保険に切り替えなかったんですが、
急に保険証が必要になり、お金を納めようと思っています。
■だいたい一月にどれくらい納めるものなのでしょうか?以前は年180万程度の収入でした。又、減らしてもらえるでしょうか?
■すぐに保険証、又は代わりの物などは発行してもらえるのでしょうか?
・11/30退職なら、制度的には、12/1に市町村の国民健康保険に加入しています。
・国民健康保険は市町村ごとに独立した運営ですので、計算方法も市町村ごとに違います。違いが大きいので「大体」とか「相場」も出せません。
・国民健康保険料/税は、健康保険料のような「何月分」ではなく、「今年度のこの世帯の額は幾ら」という形で、それを分割払いします。(納付回数も大抵の市町村では12期ではありません)
質問者の場合は、12ヶ月加入した場合の額の4/12を納付するよう求められます。
・小規模な市町村では、窓口に保険証を作る機械がなかったりします。その場合には、資格証明書になるでしょう。
・国民健康保険は市町村ごとに独立した運営ですので、計算方法も市町村ごとに違います。違いが大きいので「大体」とか「相場」も出せません。
・国民健康保険料/税は、健康保険料のような「何月分」ではなく、「今年度のこの世帯の額は幾ら」という形で、それを分割払いします。(納付回数も大抵の市町村では12期ではありません)
質問者の場合は、12ヶ月加入した場合の額の4/12を納付するよう求められます。
・小規模な市町村では、窓口に保険証を作る機械がなかったりします。その場合には、資格証明書になるでしょう。
失業保険 旦那の扶養から抜ける?
妹が失業保険を5月から120日間貰う予定です。
すでに5月半ばに1回目の14日間が給付され、6月(28日分)、7月(28日分)、8月(28日分)、
9月(22日分)で120日です。
妹は
旦那の扶養に入ってます。
120日給付されても48万程度です。
2012年は1日も働いてないので収入は0です。
もし9月以降も働き口が見つからなければ収入は失業給付金のみの48万です。
お聞きしたいのは妹の旦那の保険組合は1か月に10万越えたら扶養から外されるではなくあくまでも年間で130万以下なら扶養に入れるが規定と言われてます。
この場合別に扶養脱退申告をしなくてもバレないと思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに去年の年末調整の紙には2012年の妻の予定収入は0と言ってあります。
何故なら12月末日で仕事を辞めたからです。
どなたかお知恵をお貸しください。
妹が失業保険を5月から120日間貰う予定です。
すでに5月半ばに1回目の14日間が給付され、6月(28日分)、7月(28日分)、8月(28日分)、
9月(22日分)で120日です。
妹は
旦那の扶養に入ってます。
120日給付されても48万程度です。
2012年は1日も働いてないので収入は0です。
もし9月以降も働き口が見つからなければ収入は失業給付金のみの48万です。
お聞きしたいのは妹の旦那の保険組合は1か月に10万越えたら扶養から外されるではなくあくまでも年間で130万以下なら扶養に入れるが規定と言われてます。
この場合別に扶養脱退申告をしなくてもバレないと思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに去年の年末調整の紙には2012年の妻の予定収入は0と言ってあります。
何故なら12月末日で仕事を辞めたからです。
どなたかお知恵をお貸しください。
年末調整では失業手当は非課税なのでかまいません。社保等の扶養には年末調整とは関係ありません。
一般的には3612円以上なら扶養から外れなければならないと言われています。しかしあくまで一般的にであって、その判断は扶養者の所属する保険組合や会社の判断です。正式に本当に失業手当の月額も日額も関係ないと会社がいうのであれば扶養からはずれる必要はないでしょう。違うのに黙っていてバレなければいいのでは、不正してもいいかというのであれば自己責任です。誰も不正行為に大丈夫ですよとは言えません。ここは不正行為のアドバイスをするところではありませんので。
いずれにせよ、ここで聞いても意味がありません。
一般的には3612円以上なら扶養から外れなければならないと言われています。しかしあくまで一般的にであって、その判断は扶養者の所属する保険組合や会社の判断です。正式に本当に失業手当の月額も日額も関係ないと会社がいうのであれば扶養からはずれる必要はないでしょう。違うのに黙っていてバレなければいいのでは、不正してもいいかというのであれば自己責任です。誰も不正行為に大丈夫ですよとは言えません。ここは不正行為のアドバイスをするところではありませんので。
いずれにせよ、ここで聞いても意味がありません。
退職後の手続きについて
退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました
(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)
まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました
(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)
まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
税金は、11月の退職ですと、年末調整対象外になりますから、来年確定申告を行なうことになります。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。
社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。
退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。
健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。
退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
このとき源泉徴収票が必要になり、後は、今までの年末調整時に提出していた生命保険の払込証明等同じものが必要になります。
もし 12 月から国保、国民年金の納入をしていれば、これも控除対象になります。
昨年の収入に対する住民税は、11 月までは源泉徴収で納入していますが、12月分以降来年 5月分までは、納入できなくなります。
この処理は二種類あって、退職金から引いて会社が代わりに納入することもありますが、これをやらない場合は、市町村役場から請求書が来ますので、その時点で納入すれば済みます。
社会保険のうち年金は、現在の厚生年金から外れ、国民年金に自動以降となるので、待っていれば社会保険庁から書類が送られてきます。
来たら読めば処理はわかると思います。もし会社に年金手帳が預けてある (企業によって違います) のであれば、退職時に必ず貰っておいてください。
退職時には、離職票 (退職後一週間程度かかるかもしれません)、雇用保険証、源泉徴収票を貰ってください。
健康保険ですが、現在加入している健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に移るか、と言うことです。
前者であれば、現在は雇用者、加入者が折半している保険料を全額負担 (簡単に言えば倍になります) してそのまま使用するか、止めて国保 (保険料は前年収入で決まります。これは住民登録してある市町村役場に問い合わせればわかります) に切り替えるか、と言うことになります。
特に現在治療中の疾患がなければ、保険料の安い方を選べばいいと思います。
任意継続の場合は、新たな保険組合に加入 (再就職と考えてもらって結構です) しない限り (何年間までの) 期限までは脱会できませんが、(確か四半期ごとだった) 保険料納入をしないとその時点で自動脱会になります。
国保は、脱会するときは自分で手続きしないとなりません。
退職金があっても、これは税計算が別で、源泉徴収されてそれでお終いです。
退職後、再就職先を見つける意志があるのであれば、雇用保険の失業給付の手続きが必要になります。
よく勘違いされている方が多いんですが、失業したから給付されるのではなく、失業しているが就職の意思があり就職可能な健康状態であれば、求職中の生活を保障することが目的なので、あくまでも再就職先を見つける意志があることが前提です。
離職票が出たら、これと雇用保険証をもって、ハローワークへ行きますと、申請手続き (きちんと教えてくれます。三文判が必要) をしてください。
会社都合、自己都合で、待機期間、給付期間、直近半年の給与収入 (時間外等一部手当込) で給付額は変わります。
この辺りは説明してくれます。
個人事業主です。妻が他の会社を退職し、失業保険を受給しようとしています。
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
そこで質問です。
①失業保険を受給した場合、金額によって私の扶養とならないこともありますか。
その場合、私は所属する団体の国民健康保険組合に加入していますが、
妻は区の国民健康保険に加入となるのですか。
②私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合、
失業保険の受給はどうなりますか。
③失業保険の受給終了後になってから、私の(青色)事業専従者になり、給料として月額10~15万円払った場合
妻はどの保険に加入するのですか。
宜しく御願い致します。?
ご質問にもあるように
奥様が 失業給付金の日額3611円まででしたらあなたの扶養に入れますが
それ以上の金額の場合
失業給付金を受給するのでしたらご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
退職された会社に健康保険資格喪失証明書を発行してもらって手続きに行かれて下さい。
②の質問ですが、失業給付金は貰えません。
③ 専従者となった場合において あなたが加入の
団体 国民健康保険組合に聞かれて下さい。
奥様が 失業給付金の日額3611円まででしたらあなたの扶養に入れますが
それ以上の金額の場合
失業給付金を受給するのでしたらご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
退職された会社に健康保険資格喪失証明書を発行してもらって手続きに行かれて下さい。
②の質問ですが、失業給付金は貰えません。
③ 専従者となった場合において あなたが加入の
団体 国民健康保険組合に聞かれて下さい。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
関連する情報